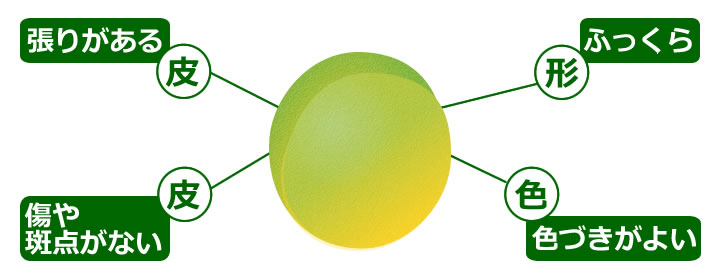ウメ 梅 Ume
基礎データ DATA
梅の旬(出回り時期)
※これは梅の出回り量の割合をグラフ化したものです。農林水産省統計 青果物卸売市場調査 品目別:主要卸売市場計(2023年)を参考にしています
梅の概要

梅は日本人の食卓に欠かせない食物の1つといえるでしょう。梅干しや梅酒、カリカリ梅などさまざまな用途に加工でき、梅特有の酸味と香りで味覚を楽しませてくれます。
生梅が出回る時期は短いですが、シーズンになると店頭にはたくさんの梅とともに大きな瓶や氷砂糖なども並んで季節を感じさせてくれます。
梅の歴史

梅は中国が原産で、日本へは奈良時代に中国から伝わったといわれています。当初は観賞用でしたが鎌倉時代には梅干しとして食用されていたそうです。広く注目されるようになったのは江戸時代で、本格的に栽培され始めたのは大正に入ってから。昭和30年頃からは品種改良が進み、また昭和37年には酒造法の改正により梅酒の自家製造が可能になったことで、梅の需要がグッと伸びました。
梅の栄養と効能
おもな栄養成分(可食部100g中)
カリウム(240mg:生梅/440mg:梅干し)、βカロテン当量(240mcg:生梅/83mcg:梅干し)
注目成分
クエン酸、リンゴ酸
期待される効能
疲労回復、食中毒予防
熟した梅はクエン酸やリンゴ酸を含んでいるので疲労回復に効果があります。特に梅干しには高濃度のクエン酸が含まれています。ただし塩分も多いため梅干しの食べ過ぎには注意しましょう。
また梅に含まれる有機酸には殺菌効果があり食中毒の予防に有効と考えられています。
より詳細な栄養成分については、「栄養成分(グラフ)」もしくは「栄養成分(一覧表)」に掲載しています。
栄養成分表を見る
梅の種類
南高(なんこう)

日本一の梅の産地である和歌山県の代表的な品種。果皮は緑色で完熟すると黄色から赤味を帯びます。サイズは25~35gくらいで肉厚でやわらかく、おもに梅干しや梅酒として使われます。明治35年に和歌山県の上南部村の高田氏が発見し「高田梅」として育成。その後南部高校の竹中氏などによる調査で選抜され、昭和40年に「南部の高田梅」ということで「南高」と名称登録されたそうです。出回り時期は6月中旬から。
白加賀(しらかが)

関東地方に多く流通している青梅で、サイズは25~30g程度。果皮は淡黄緑色で、肉厚で緻密です。旬は6月中旬からで、用途としては梅干しや梅酒、梅シロップなどに向いています。江戸時代から栽培されていたようですが来歴は不明です。
古城(こじろ・ごじろ)

南高とともに和歌山県で多く栽培されている青梅です。果重は25~30gほどで果皮は緑色。梅酒や梅ジュースに適しています。大正時代に和歌山県の長野村の那須氏が発見し、那須氏の屋号から「古城」と名付けられたそうです。
小梅

5g前後の小さな梅で、品種としてはおもに長野県で栽培されている「竜峡小梅」や、山梨県で栽培されている「甲州小梅」などがあります。出回り時期は5月下旬からで、梅干しやカリカリ梅などに用いられます。
各地の年間収穫量 梅
円グラフと下表の割合(%)が違うときは?
上の円グラフの割合(%)と下の表の割合(%)の数値が違うことがありますが、その場合は下表のほうが正しい数値です。
下の表は出典である農林水産省のデータに記されている「全国の合計値」から割合を計算したものです。
上の円グラフも農林水産省のデータですが、こちらは全国ではなく主要生産地のみのデータなので、値が公表されていない都道府県は含まれていません。
また、ページ上部の「基礎データ」にある「おもな産地」の数値は、下表の割合(シェア)を四捨五入したものです。
出典:農林水産省統計
2023年の梅の収穫量のうち最も多いのは和歌山県で、約6万1,000トンの収穫量があります。2位は約5,520トンの収穫量がある群馬県、3位は約1,730トンの収穫量がある福井県です。
栽培面積・収穫高の推移
出典:農林水産省統計
2023年の梅の栽培面積は約1万3,200ヘクタール。収穫量は約9万5,500トンで、出荷量は約8万4,600トンです。
品種ごとの作付面積
出典:農林水産省統計
2022年の梅の作付面積は、1位は南高で約4,642ヘクタール。南高だけで全体の半分以上を占めています。2位は白加賀で約1,017ヘクタール。3位は小粒南高、4位は紅サシとなっています。
主要生産国(上位5か国)
出典:FAOSTAT(2023年)
アンズ(ウメ)生産の上位5か国は、トルコ、ウズベキスタン、イラン、イタリア、アルジェリアです。1位のトルコの生産量は年間約75万トンで全体の約20%を占めています。2位のウズベキスタンは年間約50万545トンで全体の約13%、3位のイランは年間約31万8,475トンで全体の約9%です。
果物統計のページに移動